| 日本茶の種類と特徴を紹介します |
|
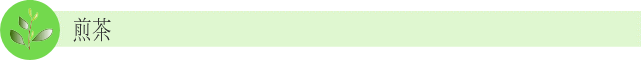 |
柔らかい新芽の部分を原料にした、日本緑茶の中でも最も一般的で基本的なお茶です。
上級茶ほど、うま味、香りがあります。
また、適度に渋み・苦みもあり、後味も爽やかです。
5月の初摘みは新茶として出回ります。
初摘みの葉は、冬の間蓄えた養分がしっかり詰まっていますので、独特の味わいがあります。
使っているのは、  (新葉)の部分です。 (新葉)の部分です。
食事のときや普段一服するときに最適です。 |
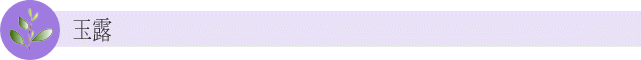 |
摘む2週間前から、お茶の木に覆いをかけ、
直射日光を避けて出た柔らかい新芽を摘みます。
覆いをかけることで、お茶のうま味成分のテアニンが増え、甘みのあるお茶が出来ます。
飲むときは60℃くらいの少量の湯でじっくり抽出し、独特のうま味と甘みを味わいます。少量をじっくり舌の上で味わう為、お茶のブランデーとも言われています。
使っているのは、  (新葉)の部分です。 (新葉)の部分です。
食事用ではなく、嗜好用です。少し特別なお茶を頂きたい方に。 |
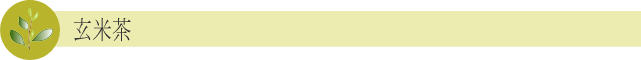 |
煎茶又は番茶に香ばしい玄米を混ぜたものです
食事のときに最適です。
|
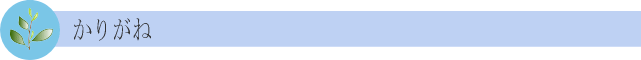 |
普通、摘み取られた葉には茎が混じっています。葉はそのまま煎茶や玉露になりますが、
上級煎茶・玉露の加工中に選別された若茎は「かりがね」と呼ばれ、これもお茶として飲まれます。
そのため価格も煎茶より安くなりますが、上品で軽快な風味を持っており、一度飲んでみる価値があります。
使っているのは、絵の  (新葉)の「茎」部分です
(新葉)の「茎」部分です
食事のときに最適です。
|
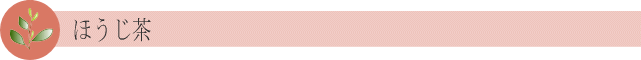 |
番茶・煎茶を強火で炒り(焙じ)、香ばしい香りを出したものです。
番茶・煎茶の材料によって、香り・味の違いがあります。
使っているのは、絵の  (新葉)と (新葉)と  (葉)の部分です。 (葉)の部分です。
食事のときや普段一服するときに最適です。 |
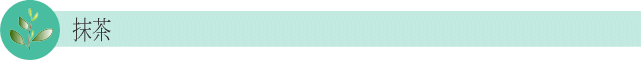 |
葉を石臼で挽き、粉末にしたもので、主に茶道に使います。
玉露同様、日光を避けて育てた新芽を原料にしています。
使っているのは、絵の  (新葉)の部分です。 (新葉)の部分です。
主に茶道に使います。 |
|
|
